自分の子供には幸せになってほしい。
勉強ができてほしい。スポーツ万能であってほしい。
お金持ちになってほしい。
親なら誰もが願っていることだと思います。
この子の為になると思って決断したこと
本当に良かったのか、もっとこうすれば良かったのではないか!
と悩んでいませんか?
実は、子供の学力向上や年収を上げる方法があるんです。
なぜなら、子供の学力を上げる方法や
年収を上げる方法には膨大な科学的根拠(エビデンス)が
あるからです。
この記事では、多くの親が切望している『勉強ができる子に育てたい』
『稼げる子』になってほしい。
この願いを実現できるようになります。
この記事を読むことでそんな親の願いを膨大な科学的根拠(エビデンス)に裏付けられた
方法を学ぶことができます。
結論、将来の収入を上げるためにすべきことは3つ!
- スポーツをする
- リーダーになる
- 非認知能力を高める
将来の収入を上げる為にすべき3つのこと
・スポーツをする
将来の収入を上げる為にすべきこと1つ目は
スポーツをすること!
これにはしっかりとエビデンスがあります。
パデュー大学のジョン・バロン教授らは
アメリカの高校でスポーツをしていた男子生徒は
スポーツをしていなかった同級生と比較して
高校を卒業して11〜13年後の収入が4.2〜14.8%も高い
ことを明らかにしています。
なぜ、子供の頃のスポーツ経験が、大人になってからの
収入に影響を与えるのか。
主に2つの理由があると考えられている。
採用で有利になる
ノルウェーで行われた研究に夜と、求人を出している企業
に対して、写真や経歴などは全て同じで
スポーツ経験の有無だけが違う架空の履歴書を
ランダムに送り、面接に呼ばれる確率にどのくらい
差があるのかを調べました。
その結果、「スポーツ経験がある」と書かれた履歴書を
送ると、面接に呼ばれる確率が2ポイントも高くなることが示されました。
企業はスポーツをしていた人は体力があり、そういう人を
積極的に採用したいと考えていることがわかりました。

確かに、私が面接官でもスポーツ経験のある人の方が
厳しい上下関係の厳しさに耐えられたり、コミュニケーション能力が
高かったり、粘り強さがありそうって考えるなー。
忍耐力やリーダーシップが身に付く
ノルウェーの研究では、兄弟のうち、スポーツをしているか
否かで実験をした結果、スポーツをしていた方が
将来の収入が約4%も高いことがわかりました。
このようにスポーツ経験の有無によって、賃金の上乗せ分
があることをスポーツの「賃金プレミアム」と言います。
この賃金プレミアムのほとんどが、兄弟のうちスポーツをしていた
方の忍耐力、リーダーシップ、責任感、社会性などの
「非認知能力」が高いことによるものだと分かったのです。
・リーダーになる
将来の収入を上げる為にすべきこと2つ目は
リーダーになること!
カリフォルニア大学サンタバーバラ校のピーター・クーン教授
らによって行われた研究では、高校時代にリーダーシップを発揮した
経験がある人は、そうした経験のない人と比較し、高校を卒業して11
年後の収入が4〜33%も高くなることが示されました。
もう少し、具体的にいうと高校時代に運動部のキャプテンだった
男性はキャプテン経験がない人と比較すると11年ごの収入が4.2%
高くなることがわかりました。
リーダーになると将来の採用や就職で有利になる
ベルギー北部のフランダースで行われた実験です。
企業に対して架空の履歴書を送り、どのような
経歴や経験を持つ人が面接に呼ばれるかを確かめる実験が行われた。
履歴書のパターン
- 成績は普通で、リーダー経験もない
- 成績は良いが、リーダー経験がない
- 成績は普通だが、リーダー経験がある
- 成績も良く、リーダー経験もある
パターン1とパターン3の比較
パターン2とパターン4の比較
リーダー経験があることが記載された履歴書は、面接に呼ばれる
確率が2.1~3.3ポイントも高いことがわかりました。
また、特に履歴書に書かれた性別が女性の場合に
大きな効果がありました。
優れた「上司」はチーム全体の生産量を大きく増加させ
部下が離職する確率を低下させることを明らかにした
エビデンスがあります。
リーダー経験がある人は将来の管理職候補として有望だという
サインになって、採用で有利になる可能性があるという
ことです。
・非認知能力を高める
非認知能力とは
学力テストIQテストで計測することのできる能力を「認知能力」
と呼びます。
その「認知能力」に「非ず」ということです。
英語では「noncognitive skills」と表現されます。
「能力」というよりは「スキル」と表現する方が正確ですが
日本では、非認知能力という呼び方が定着しています。
かつては認知能力が重要と捉えていた
2000年前後から「認知能力が将来の収入の変動の一部だだけ
しか説明できない」ことを示すエビデンスが増えてきました。
例えば、学力テストの個人差は、将来の収入の個人差の精々
17%程度しか説明することができず、IQの個人差に至ってはたった
7%程度しか説明できないのです。
経済学者の探究では、将来の収入の個人差を説明できる
認知能力以外の「何か」を突き止めようとしたところから始まり
それを一言で言い表そうとして「非認知能力」という言葉が
生まれたというわけです。
認知能力と非認知能力の複利効果
認知能力と非認知能力は別々のものでありながらも、両方が互いに影響
し合って、将来の学歴や収入に影響すると説明しています。
小さい頃に勤勉さを身につけた子供の方が、のちの学力が高くなりやすい。
ヘックマン教授らは、これを「技能が技能を生む」と表現しました。
これは「複利」の仕組みによく似ています。
複利とは「利子にもまた利子がつくこと」を指しています。
将来の収入を上げる3つの非認知能力
・忍耐力
子供の頃や若い頃に、忍耐力に欠けると生涯収入が13%も低くなることがわかっています。
また、学校での成績が悪く、校則違反が多く高校を中退する確率が高い。
さらに、飲酒量が多くなり、肥満になり貯蓄率が低くなることを示したエビデンスもあります。
・自制心
3〜11歳の間に自制心が低かった人は、32歳時点での健康面や経済面
安定的な生活面で不利になっていました。
子供の頃に自制心が低いと大人になった後
病気や薬物依存になりやすかったり、収入が低かったり
有罪判決を受けた割合が高いなど、多方面にわたって
悪影響があるということがわかっています。
・やり抜く力
「継続は力なり」といい、ダックワース教授は元々の才能よりも
困難や挫折に負けずに努力を続けることが重要であることを
様々なデータを用いて立証しました。
やり抜く力が強い人は、成績が良く、学歴が高く
仕事や結婚生活を継続し、定着させていることがわかっています。
非認知能力はどうしたら伸ばせるか
①音楽や美術に触れる。
ドイツのデータを使った研究によると、高校卒業まで継続的に音楽活動をしていた
生徒は、学校の成績が良いだけでなく、勤勉性が高く、外交的で意欲的であることが
わかっています。
美術館に行って、絵画を鑑賞する経験をした生徒は他者への寛容性が高く
批判的思考力に優れていることを示したエビデンスもあります。
②学校で他者に対する「思いやり」を育む
思いやりは人格の中でも特に重要で、社会全体に影響を及ぼします。
例えば、環境問題が深刻化する現代のような社会においては、自分の利益
だけを追求し、環境を破壊してしまっては、持続可能ではなくなって
しまいます。
インドのデリーで2007年に法改正が行われ、私立小学校で
貧困世帯の子どもたちを無償で受け入れることが義務化されました。
それまで私立小学校の生徒ほとんどが、経済的に恵まれた
裕福な家庭出身の子供たちでしたが、生徒全体の20%が貧困世帯の
子供達になりました。
グループワークなどで一緒に過ごす時間が長くなった生徒たちは
より寛大な気持ちを持ち、貧困世帯の同級生たちと親しく付き合ったことが
示されています。
多様な仲間たちとともに過ごし、相手の立場に立って考える経験は子どもたちの
思いやりを身につける機会となりました。
親は子育てに時間を割くべきなのか?
子育て世帯の時間貧困
共働き世帯の増加とともに問題になっているのが、子育て世代の
「時間貧困」です。
慶應義塾大学の石井加代子特任教授らの調査によると
6歳未満の子どもを育てる正社員共働き夫婦のうち
31.5%が十分な育児、家事、余暇の時間を取れない状況に陥っている
ことがわかっています。
時間投資とは
親が子どもに対して行う投資で、経済学では、お金の投資と区別して
「時間投資」と呼んでいます。
学歴の高い母親ほど子育てに時間をかけている
多くの国で学歴の高い親の方が、子どもへの時間投資が長くなる傾向が
あるということです。
イギリスで2000年に生まれた子どもを対象に行われたデータでは
母親の「勉強」への時間投資(本の読み聞かせや宿題の手伝いなど)と
「体験」への時間投資(お絵描きや野外での運動など)に分けることができます。
母親の学歴が高い方が、子どもの勉強への時間投資は増える傾向にあります。
一方、体験への時間投資は母親の学歴や雇用の両方とほとんど関係がないことが
わかっています。
時間投資の効果は子どもの年齢が小さいときの方が大きい
子どもが3歳時点では大きい勉強への時間投資の効果は
7歳時点ではほとんどゼロになっています。
とはいえ、3歳時点の時間投資の効果は、その後も持続
するようです。
3歳時点で行われた勉強への時間投資は、ことばの発達に影響を与え
それが、5歳や7歳の時の認知能力を伸ばすことの助けになるということが
起きます。
子どもの年齢が小さい時の時間投資の効果は持続しますが
持続力が高いのは認知能力よりも非認知能力への効果です。
イギリスの生活時間調査のデータから、子どもの年齢が7歳や
11歳になった時点でも、親の時間投資が非認知能力に与える効果は
大きく、特にスポーツや読書、掃除や片付けなど、親と一緒に活動的に
過ごす時間に意味があるようです。
祖父母と同居すると孫のコミュニケーション力や学力が上がる
祖父母と同居することは、孫のコミュニケーション力や言語発達に
良い効果がある一方、肥満になりがちであることを示すエビデンスが
あります。
台湾で行われたデータでは長期間、祖父母と同居した子どもは
学力が高い傾向にあることを示しています。
また、祖父母と孫が一緒に過ごす時間が10年伸びると、孫が高校を卒業
する確率が7ポイント上昇することがわかりました。
フィンランドの研究では、祖父母が具体的にどのように
孫を助けているのかを明らかにしています。
父方の祖母について、祖母自身が持つ親戚のネットワークを駆使し
孫の学歴が高くなるよう仕向けます。
母方の祖母については、親が離婚したり、収入が減ったりした時など
家族の危機が生じた時に孫を助けることで、学歴に良い影響を与えます。
第1子は第2子よりもデキがいい
アメリカのメディアでは「第2子の呪い」と呼ばれています。
コロンビア大学のサンドラ・ブラック教授の研究では、生まれ順が後の子ども
ほど、将来の学歴が低くなることを示しました。
また、生まれ順があとの子どもほど犯罪で逮捕される確率が上がる
ことがわかりました。
デンマークの研究では、長男よりも次男の方が成人までに犯罪に
関わる確率が3.6ポイントそして、刑務所に服役する確率が2.7ポイント
高くなることがわかりました。
そして、生まれ順があとになればなるほど、フルタイムで雇用される確率が低く
収入も低くなる傾向があるといいます。
親自身が第1子だった場合、その子も学歴が高くなることが示されています。
第1子が有利になることを示す4つの仮説
仮説① 親の投資時間に差があるから
「親の投資時間」に差があるから。
アメリカの生活時間調査のデータでは、第1子と第2子が同じ年齢のときの
親の時間投資に差があるかどうかを計算すると
第1子の方が平均して1日あたり20〜25分も親と長く過ごしていることが
わかりました。
これを4〜13歳の期間に換算すると、第1子と第2子の間では、親と過ごす時間が
2200時間近く異なることになります。
なぜこのようなことが生じるのでしょうか。
親は、それぞれの子どもに対して平等に時間配分しようとすることが
挙げられます。
この結果、第2子が第1子の年齢に達した時に第2子が親と過ごした時間は
当時の第1子よりも少なくなってしまいます。
平等であろうとすると、生涯を通してみれば、第1子と過ごす時間が
長くなってしまうのは当然のことです。
仮説② 非認知能力に格差が生じるから
スウェーデンの研究では、第1子は情緒が安定しており、粘り強く、外交的で
責任感が強く、様々な物事においてイニシアチブをとる傾向が強いことが明らかに
なりました。
第1子は将来管理職に就く確率も高く、45歳時点で企業の社長になる
確率が28%も高いということがわかりました。
仮説③ 親のしつけに格差があるから
第1子の成績や行いが悪かった場合に、より厳しくしつけをしたり
見守りの度合いを強めたりします。
それは、第1子のためだけでなく、下の子がサボったり、悪いことを
しないよう「抑止」するためでもあるといいます。
アメリカの研究では、親が第1子の行動の見守りをしている時間は
下の子どもたちよりも長いことが示されています。
仮説④ 予想外の妊娠だったケースが多いから
第1子と比較して、第2子の方が予想外の妊娠だったケースが多いため
格差が生じているという仮説です。
つまり、子どもの教育に対する十分な準備ができていなかった
可能性があります。
一人っ子にもデメリットはある
1979年から中国で導入された「1人っ子政策」の帰結を分析した研究によると
1人っ子政策が導入された、1979年より後に生まれた子どもの方が
競争心が弱く、他人を信頼する気持ちに欠け、リスク回避的な傾向が
強いことがわかっています。
仮説③で記載した通り、第2子のための「抑止」から行う
しつけの面から考えても、兄弟間の格差が生じることを恐れて1人っ子
にするよりは、下の子が小さい時に親の注意や監視、お金や時間が
上の子と同じように下の子にも注がれているかどうかを意識
することが大切です。
第一志望のビリと第二志望の1位 どちらが有利なのか
優秀な友達から受けるのは「良い影響」だけではない
優れた友人から良い影響を受けるのは、もともと学力が高い児童・生徒だという
エビデンスがあります。
アメリカの空軍士官学校のデータを用いた実験。
グループ①
学力が上位層の候補生と下位層の候補生が一緒になった戦隊
グループ②
学力が中間層の候補生のみの戦隊
グループ③
完全にランダムに選ばれた候補生の戦隊
最も成績が上昇したのはグループ②でした。
自分と共通点の多い同級生の間では交流が生じやすく
お互いに多くのことを学ぶことができるということが
わかりました。
グループ①は平均的な成績が上がらなかったばかりか
もともと学力が低かった候補生の成績は
更に低下してしまいました。
小学校の学内順位は最終学歴や将来の収入にまで影響する
『仮説①』 親や教員からの扱いが違うから
順位が高ければ、親や教員からの期待が高まり
教育にお金をかけてもらったり、学校で特別扱いを
受ける。
しかし、この仮説は多くの研究者から否定されています。
親は、順位が高いほど学校外にかけるお金を減らす傾向に
あるからです。
アメリカでは順位が高い子どもに対しては
宿題の手伝いを減らすことがわかっています。
『仮説②』 子ども自身の「自身」に影響を及ぼすから
順位は子どもたちの「自己効力感」(自分ならきっとうまく
できる、自分の可能性を信じていること)に影響を
及ぼしていることがわかっています。
順位は「前回と比べて」どれだけ伸びたかを伝えるのが正解
上記の仮説では、順位は知らせないほうが良いのでしょうか。
成績順位を通知すると学校やクラス全体の平均的な学力が
高くなるエビデンスはあります。
しかし、あくまで集団全体の平均の効果であって
順位が低い生徒や学生に対する悪影響は避けられません。
前回と比べてどれだけ伸びたかを知らせることで
その後の生徒の平均的な学力が高まったことを示す
エビデンスがあります。
まとめ
将来、子どもが成功するためには、非認知能力を高めることが重要です。
非認知能力を高めるには、スポーツをしたり、リーダー経験をしたり
音楽や美術に触れることで高められます。
学校では他者への思いやりを学び、自身の成長につながる環境に
身を置くことが重要です。
親として、大事なことは子どもを育てる環境を整えることが
重要な役割であり、最も考えなければならないことだという
ことがわかりました。
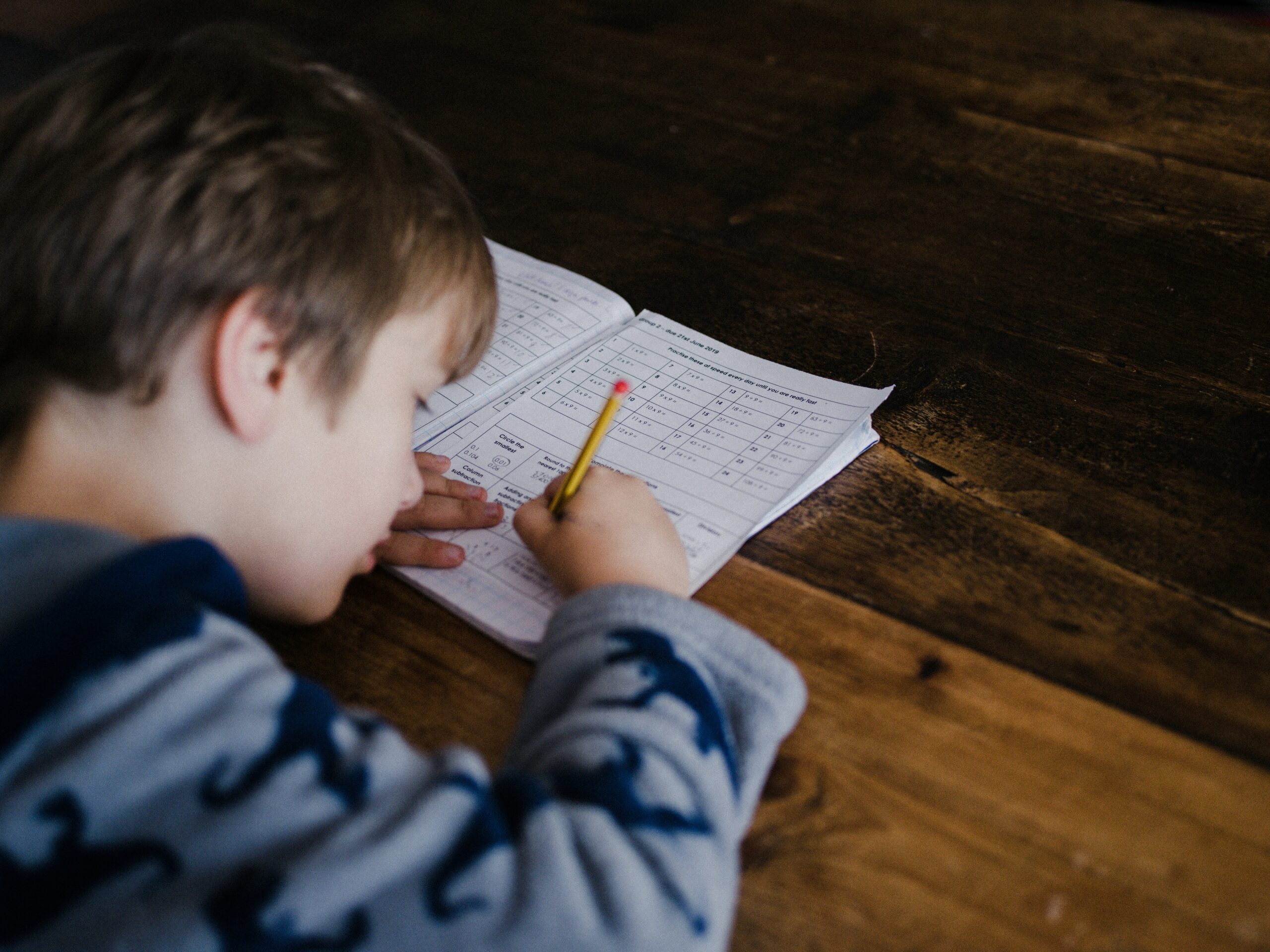

コメント